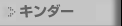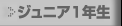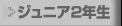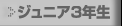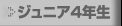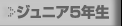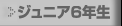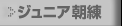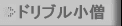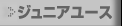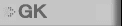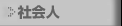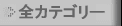先日ラジオ関西「ラジオ講座:ひょうごカレッジ」に出演し題目「変わること」でお話しました。
まだお聴きでない方は聞き逃し配信(津田HPに掲載)されています。
汚い声でお聞き苦しいですがよかったら聴いて下さい。
子育て(ママパパ)学習会
12月7日(土曜日)・津田公民館・19:30~20:30
<はじめに>
- ラジオ関西「ラジオ講座」収録エピソード
- 姫路市教育振興基本計画審議会の「審議委員」として参加報告
<本日テーマ>
平成14年度から続いてる「子育て教室」での保護者アンケートから
「悩みごと」3点を選び学習会のテーマとしました。
(1)子育てを「どうしたら…」と悩んでる
・子どもが反抗的、口答え、学校へ行きたがらない。甘やかせてしまう。
・幼児の時にうまく躾けられなかったことを未だに後悔している。
(2) 人間関係作りが苦手で悩んでる
- 話すのが苦手でうまく喋れず相手に思いが伝わらない。
- 勤め先、家庭、親族間などの人間関係作りが苦手。
(3)自分自身が「イヤ」で悩んでる
- 自分の容姿(外見)が「イヤ」見栄っぱりなのも「イヤ」
- 一人(孤独感)がイヤなのに人といると疲れるのが「イヤ」
- 劣等感の固まりでネガティブな自分が「イヤ」
<まとめ>
- 人は人に傷つけられるが人に癒される。
- 子どもの成長は出会った大人(指導者)によって大きく影響を受ける。
(お知らせ)
・中学校部活動く地域移行>について
26年度より中学の部活動が地域に移行されます。
現在わかる範囲での展望をお知らせします。
(過渡期にあたる現:5、6年生の保護者はぜひ参考にして下さい)
*当日はスマホを持参して下さい。
津田以外の友人、知人もお誘いぜひ一緒にご参加下さい
エストレラ津田サッカークラブ代表
NPO日本教育カウンセラー協会公認カウンセラー
樽本直記

令和6年度 『育成会総会・子育てママ教室』
◯1部 挨拶
エストレラ津田サッカークラブは今年創部50年めを迎えます。
公立高校(主に福崎高、琴丘高)の部活動で「全国出場」の夢を見ながら地域クラブチーム(津田、エストレラ)を運営するという当時は誰もやっていなかったいわば「二刀流」をなし遂げるべく活動を続けてきました。
一方カウンセラーとして不登校や引きこもりの子どもに寄り添いながらお母さん対象に「子育てママ教室」、中学生には「メンタルセミナー」を開講、放課後ディサービスでは障がい者の子どもたちと過ごしてきました。
今、振り返ってみると子どもたちのために「あっ」という間の50年でした。
◯2部 子育てママ教室
(1)「子育て」に正解はない。
10歳(半成人)になれば子離れを始め、あとは子どもに任せる(自立)
(2)「子育て」とは(興味、関心)事を持たせること。
子どもには好きなことをトコトンさせよう。
(3)「子育て」は待つ、忍耐、我慢すること。
子育てに終わりはなく一生続くからこそがんばりすぎず楽しもう。
(4)「子育て」は子どもの「心音(こころね)」を聴く。
子どもの行動には必ず意味がある。言語力のない幼児(泣くしかない)
うまく話せない思春期の子(怒り)の行動には受容の心で。
(5)「子育て」を通じ親が変わること . . . 変わりましょう。
◯3部 「親はなくとも子は育つ…」
(1)手を繋いで三者面談(進路)にやってきたN子とおばあちゃん。
難関の公務員試験を見事突破「就職祝いと祖母の誕生日会」は我が拙宅で。優しさとあたたかさを持ったN子。目元はおばあちゃんそっくり。
(2)ヤングケアラー
お母さんのお世話のために入院先に近い高校を選んだY子。家事炊事をこなしていた甲斐もなくお母さんと永遠の別離が . . .
お別れの日「笑顔」で見送るY子の姿が . . .
私への手紙には「お母さんが一番喜ぶのは私の《笑顔》だから . . . 」お母さんは遺産としてY子に《笑顔》を残して徃った。
(3)幼くして母親の愛を知らず長期寝たっきりだった父親の葬儀を出すことに。彼女の手紙「たるさん、親って?家族ってナニ?!」の問いに答えられない。
高校生にして身寄りがなくなり一人で生きていくしかなくなった。彼女の幸せを祈るしか。。。(何もしてあげれない無力感だけが . . . )
◆子育てママ教室◆(津田育成会総会)
コロナ期に開催できずにいた育成会総会の後の「子育てママ教室」では
サッカ-好きな子を(1)指導者と(2)親(育成会)が連携を取って子どもを見守っていくことを確認しました。
(1)指導者(先生)
子どもの苦しさに気づく大人(親、先生)がそばにいてあげること。
私は高校教師時代、授業は勿論のこと、学校生活やクラブ活動など日常の会話に至るまで生徒の発信する信号(言葉、行動)に気づくことを意識していました。
「気にかけてるぞ」「苦しい時は遠慮せず話をしてくれ」「一人で悩むなよ」と願いながら寄り添うようにしていました。
交換日記、レポ-ト、手紙、面談、雑談、家庭訪問などあらゆる手段を使って
「樽さんなら話してもいい、話してみたい」と思ってくれないかなぁ、、、と。
少年サッカ-の指導も50年近く子どもたちの関わりに対しても同じスタイルで、指導者にも機会あるごとに「とにかく気づこう」と話し合っています。
「気づき」は指導者も親も持っていないといけない「感性」です。「気づき」のポイントは子どもの動作、しぐさ、声のト-ンなど多種多様にあります。些細なことでも決して見落としてはなりません。
(2)苦しかったら逃げろ、、、
ストレスから逃れる術(すべ)を知らない子どもは嫌なことが「イヤ」と言えず我慢に我慢を重ねている。そんな子は親や周りに心配かけまいといじらしく、心優しい子(弱いと言われるが)に多く見られます。
何でも話せる友だちがいることは重要ですが、あくまでも同年代であり、受け入れる子どもの度量にも限界があり問題も起こります。
話をしても友だちに困惑されたり迷惑がられるケ-スもありその結果、仲間外れになり、時には「いじめ」へと発展することもあります。
(3)聞いて聴いて(傾聴)、、、待って(自立)
子どもはイライラが募ればいつかは爆発し反社会的(暴力、非行)行動に、抑圧すぎると非反社会的(孤立、引きこもり、不登校など)行動に出ます。
そうなる前にまずは聞きましょう。話しやすい雰囲気を作り最後まで聞くこと。
聞いてあげると大人(指導者、親)を信じることで子どもは安心します。子どもが心の中を開示すれば、その後は大人の指示、指導(誘導)は不要です。
子どもが自分で考え選択し動くまで〔待ちましょう〕躾け、教育は「忍耐」です。
(4)親、家庭
子どもが「家に帰りたい、ほっとできる家がいい」と思ってますか??「家」は子どもが成長する場であたたかい雰囲気作りが最も大切です
*家庭は人間の基本的欲求
(ア)食欲(イ)睡眠欲(ウ)活動欲の充足の場
子どもが美味しい好きな物を食べ、ゆっくり休んで、好きなことをする場。
*家庭で親が絶対に口にしてはいけない(否定的な)言葉
(ア)他人や兄弟との比較(その子にはその子の良さを見落とさない)
(イ)過ぎた過去をしつこく言わない(子どもは未来、希望に生きてる)
(ウ)恩にきせない(してやってる…)親の仕事を全うし感謝を要求しない。
※子どもは親と先生(指導者)は選べません(だから責任があります)
親を頼りに産まれた、神様から授かり物の子どもに明るい未来が来ますように!(祈)
「子育てママ塾」 ・令和3年2月8日
緊急事態宣言が継続されました。コロナで一度も「子育てママ塾」の開講が
できていません。早く収束し共に研修したいものです。
*以下は勤務していた高校での保健体育の授業で実施した女子高校生対象の
◆アンケ-ト結果「ベスト10」◆です。
<テ-マ>は
※家に帰りたくない、おもしろくない、こんな親はキライだと思う時は、、、
〔第1位〕夫婦ゲンカ。
*いつも子どものいる前で。
「お父さん、お母さんどっちが好き」なんか聞かないで(困るだけやんか)
〔第2位〕家での居心地が悪い。
*家でホッとできない。部屋は雑然としてるしバタバタしてて落ちつかん。
〔第3位〕最後まで話を聞いて。
*聞いてる?と思うと急に説教に変わる(聞いてくれるだけでいいのに)
〔第4位〕おかあさんのグチ。
*おとうさんや仕事、祖父母や兄弟のことで毎日のように文句が、、、、
(聞いてあげたらいいのはわかるけど、私もしんどい時があるんや)
〔第5位〕あんたのために(働いてるとか、してやってるとか)
*恩に着せないで(言わないけど「大変やろな」と感謝してるんやで)
〔第6位〕なんでそんな言い方、頼み方はなん??
*感情的で命令調で(したくなくなるわ)
〔第7位〕「あんたなんか、、、」に続く言葉はなんなん?
*産まなくてよかった?それともいらん?(それって言ったらアカン言葉やで)
〔第8位〕朝から機嫌が悪い。
*昨夜からまだ怒ってる。気持ちよく「おはよう」言ってよ。
「いってらっしゃ-ぃ」と送って(そしたら素直に「ゴメン」が言えるのに)
〔第9位〕たまにはごはんや弁当作って。
*忙しいのはわかるけどオカンの〔手料理〕も食べたいわ。
〔第10位〕子どもの頃はほめてくれたのに。
*悪いとこや失敗ばかり探して(性格が悪いと言われても=あんたの娘やで)
〔番外編〕*言い方で子どもは間逆な感じ方になる。
(1)ものは言い方(例)「自分の好きにしたらええで」と言っても
○「自分で考えて選んでええで。決めたらがんばりや」と応援してる。
×「好きにしたらええで(勝手にしぃ。お母さんもう知らん)」それって
「ええで」と言いながら怒ってるやん!(親の思い通りにならへんから?)
(2)「あんたのことを信じてる」と言いながら。
「やっぱりな」とか「また、するやろう?」と疑ってる。信じてない証拠や。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
※上記のアンケート約150人中<半数>は「家が好き、親が好き」と返答。
わが子にもそう思ってもらえる家庭(親子関係)にしましょう。
今は可愛い少年。でももぅすぐ難しい思春期(中学生)から高校年代へ。
お母さんも子どもの頃を思いだし心に〔傷=トラウマ〕となる言葉は控えて。
「あの時こうしておけば、、言わなければ、、」と後悔のないように。
子どもはやがて旅立ち、いつまでも一緒には暮らせません。
「子育て」を今一度振り返り、一緒に過ごせる喜びの日々を大切にしましょう。
「子育てママ塾」
「子育てママ塾」が一度も開催できていません。少年の心を整える「こころ塾」や
中学生対象の「メンタルセミナ-」さえも。実施したいが、第3波が?、、、
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この秋予定していた「子育てママ塾」のレジメです。お役に立てれば幸いです。
◆テーマ「思春期(少年後期~魔の14、15才)」をどう乗り越えるか?◆
※思春期(第二反抗期)の子どもは悩みと葛藤の繰り返しの毎日です。
何をするにも迷い右往左往し進むのに時間がかかります(これが本来の姿)
そして夢(理想)と現実(自分の力)との差(ギャップ)に気づき苦しみます。
そんな時つい「学校へ行きたくない」と口にすると親は驚き動揺を隠せません。
「なぜ?」の問いに「わからヘん、でも、、、」とハッキリしない態度に対し
早く解決したい親は「何があった?何がイヤなん?」とたたみかける。
「別に理由ないし、、、」との子どもに親は「こんなに心配してるのに(怒)」
「理由がないなら行きなさい、みんな行ってるでしょ」と子どもの心音(本心)を
分かろうとせず突き放すとそこに親子の間に不穏な空気が流れ「溝」ができる。
思春期の子どもは様々な事がからまり答えが出ずに苦しんでいる。
子どもがしてほしくない友だちと比べられ、やがて「勉強?」の話へ移っていく。
するとイラダチが押さえられず問題行動に、また発散できない子どもは不登校に。
「うちの子がこんなことになるとは、、まさか、、」とそこで気づく。
※「子どものため」と言いながら言葉巧みに誘導することも子どもは気づいてる。
「ほっといてくれ、うざい」と言うと親は怒り心頭。決まり文句である
「じゃ、好きなようにしぃ、勝手にしたらエエ。お母さんもう知らん」となる。
そして親が無理やり決めたことを途中で「やめたい」と言うものなら
「あんたが決めたことやろ」と逆切れ。こうなると親への相談は今後なくなる。
その一方で好きな親の意見に従うと親はとっても機嫌がいい。
その親の姿を見て子どもも安心する(意見に従っていれば子どももラクだし)
そうして(親への忖度で)自分で考え意思決定ができない子どもに育つ。
「それってどうなんでしょう?親の傘に隠れ庇護され続ける子どもの未来は?」
「いつ子離れをし自立させるのですか?」★「10歳自立式(半成人)ですね」
※まとめ※
思春期=壁にぶつかり考えもまとまらず「どうしょう?」の不安な毎日。
親は昔子どもだったことを忘れて(しつけ)と称して親の〔おしつけ〕の連続。
あせらずに話しやすい雰囲気を作り聞いてあげてくれたら、それからあとは
本人が解決するまで寄り添い待ちましょう★「子育ては我慢、待つことです」
ただ子どもは先をあまり考えず「友だちがしてるから」と安易に同調し簡単に
行動しがちです。そうなりそうな時は親のアドバイス(情報)が必要です。
正しい情報をしっかり集めて子どもに提示して考え判断する材料にしてあげて。
●樽さんからの情報提供3つ●
(1)サッカ-界周辺の情報提供
少年、ジュニアユ-ス、高校から社会人まで46年携わってきました。
そのチ-ムの指導体制、方針、指導者の様子などはわかっているつもりです。
(2)思春期年代のメンタル教育(心の強化)と悩みの相談窓口提供
教育カウンセラ-資格を生かし長年教育相談に携わってきました。
悩む子どもたちといることは経験上慣れています。任せて下さい。
(3)将来の進路指導の提供(親も子も一番気になる)
高校現場43年から数多い経験出会いで進路指導(高校、大学、就職)が可能です。
人生の「道しるべ」になってあげたいです。思春期のこの時こそあずけて下さい。
<追伸>
子どもや親の悩み、進路の相談をよく受けていましたが今年はほとんどなく
寂しい思いをしています(やはりコロナか?)ぜひ遠慮なさらず訪ねて下さい。
美味しいアメツチのコ-ヒ-と(ケ-キ?)で待っています。
「子育てママ塾」
ーーー緊急メッセ-ジーーー
休校が明けました。そこでぜひ伝えたいことがあります。
この1週間はできる限り子どもといる時間を作ってどんな小さなことでも
気づいてあげて下さい。
「もっとがんばれ、さぼるな」などネガティブ言葉は避けて下さい。
子どもは3月休校になる時は「ラッキ-」程度に思ってたが4月まで続くと
仲間と離れた孤立感や自由に活動できない不安さが現れてきました。
5月なれば日常生活に戻れると思ったのにさらに1ヵ月続くとなると、、、
約3ヵ月間、家でも周りでもコロナ、TVをつけると毎日のように感染者数や
死亡者数など暗くて苦しくなる報道が聞きたくなくても耳に入る.
そんな生活が続くと口に出さずとも不安で不安でたまらないはずです。
そんな中での学校再開です。
学校は1年間をかけて教える内容を9カ月余りで消化しないといけない。
遅れを取り戻そうと急ぎ、1日の時間数も増やし詰め込もうとします。
再開を楽しみしていた子どもにとって学校の現実がまた大きな障壁となる。
学校行事や様々な体験は子ども同士の関わりは学習以上に大切なはずです。
なのに一生の思い出になるはずの運動会、音楽会、自然学校、林間学校から
修学旅行」までが中止になる恐れが出てきています。
毎年待ちに待ってる「夏休み」も半減、中学など1週間余り。
猛暑の中、熱中症を恐れ重いカバン背負って通う姿を想像すると親も辛い。
長期の「気分転換」のはずだった夏休みがストレスになることは避けたい。
「僕らの年は学校行事はほとんどなかったし、夏休みに旅行や遠出することも
少なく楽しかった思い出がない」と大人になってからの会話では悲しすぎる。
新型コロナの収束は見通せず第2、第3波もやってくると思われます。
感染症も怖いですが子どもがストレスから精神的に病むことがもっと心配です。
これからの行動は「3密」を避けて手洗いマスクなど対策を立てながら
感染症を深刻にとらえすぎ細かく注意しすぎると子どもに不安さが残り
思いっきり行動ができないこともストレスの原因の一つになります。
特にまじめな子は親や学校の言うことを頑張って守ろうします。
そこはまだ「わがまま言いたい放題」の年齢の子どもであるはずです。
「ムリしてないか、ストレスを発散しているか、楽しんでるか?」
100年に一度あるかないかの大きな混乱の中で過ごしている子どもに
今こそ「心のケアー」に我々大人は全力を尽くしましょう。
我がクラブができる「心のケアー」は子どもにリフレッシュや楽しさを
思う存分に発揮する場を提供をしてあげること。
こういう時にこそ(試合や大会に勝つことも大事ですが)スポ-ツは「遊び」
「遊び=たのしい」と原点に戻って気づかせてもらっています。
今こそ仲間とサッカ-できる喜びを感謝できる子どもに育てたいです。
指導者として当然ですが一人一人に寄り添い、目を配り、声をかけ
子どもたちに「笑顔」を取り戻させたい。
子どもの「明るい笑顔」でお父さんお母さんも元気をもらって下さい。
お役に立ちたいので何かできることがあれば遠慮なく聞かせて下さい。
今こそ保護者、スタッフ一丸となって子どもを見守りましょう。
エストレラ津田サッカ-クラブ 令和2年:第2号(5月)
「子育てママ塾」
*5月6日解除が5月31日まで。
子どもや家庭を守るためなら「やっぱり、、、仕方ないなぁ」
ステイホ-ムというけれどお母さんの家事、子育ての負担が増えるばかり。
三食作りから、子どもの学習が遅れないために勉強させないと、、あせる。
その我が子が思うようにしてくれないとイライラが募り我慢も限界へ。
一方旦那が協力どころか在宅勤務で子どもの生活行動をつぶさに見てしまい
叱るどころか大声で怒鳴ったあげくDVに近い行為に、それこそお母さんが
「もぅ~ええかげんにして」と叫びたくもなる。
唯一楽しみであったママ友との「お茶タイム」で発散する時間もなくなると
お母さん自身がひきこもり「おかんをやめたい---」と叫びたくもなる。
◆こんな時こそお母さん自身に〔ゆとり〕が必要です。
〔ゆとり〕を生むにはお母さんの「考え方」を変えるしかないと思います。
「わかってはいるが難しい、、、」でも変えたら楽になります。ぜひやりましょう。
*むかつき、いらだち怒りそうになったら
〔1〕まずはたるさんの「呼吸法」から。子どももやってるので一緒に。
<1、2、3>で大きく(胸を膨らませて肩を上げて)息を吸って
<4、5、6>で息を止め<7、8>で息を吐き<9、10>で吐き切るを2回。
〔2〕「学校」についての考え方
*学校の運営、方針、先生らに不満から文句の一つも言いたくなることがある。
だがこの2ヵ月、子どもといて分かる現実。給食があり、厄介な我が子に
勉強を教え、躾けをしていただける。あらためて学校ってすごいと感謝。
〔3〕「自分だけではない」という考え方
*自分が感染の恐れの中でも命がけで社会のために働いてる人たちもおられます。
少しでも休める時に休んでほしいと「感謝」の手を合わせますね。
〔4〕「我が子について」の考え方
(1)我が子とずっと一緒にいると見過ぎてしまいグチや文句が増えてしまう
<対処>片目を閉じる、たまには見ない聞こえないふりをする考え方に。
(2)ボ-ッとしている我が子(居場所は家庭)
<対処>好きなお母さんといることで「安心してるな」と考えて。
(3)好きなことしかしない我が子
<対処>特長を伸ばす。好きなことには時間を忘れてやる(集中力ができる)
好きなことは続けてやる(持続力がつく)と思って考えて。
(4)休校が続き「これから先も長いなぁ~」と思うとウンザリとなるが、、、
<対処>ふだんできないことをやらせて(言い方一つで)
「ごはんもう作らへん、やめた!」「かたづけや掃除ぐらいして!」と怒らず
「手伝って。一緒にしようか?うまくできる?きれいになったわ、さすがやな」と
褒めながら料理、洗い物、雑巾拭き、掃除、まどふき、洗濯など助かりますよ。
(5)何もしない「我が子」には「元気でさえいてくれたら」と考えて。
<対処>今熱をだし寝込まれたら大変(健康)でいてくれるだけOKと考えて。
(6)「読み書き計算」は基礎学力(強制的にでも)
<対処>子どもが社会で生きていく上欠かせない(毎日15~30分はさせて)
◎最後に:今は不要不急の外出自粛中ですが、、、
お母さんが精神的に苦しい時は不要不急ではありません、緊急事態です。
うちに来て「ぐち」を話して発散して下さい。待っています。
子どもを見て{何か変?}と感じたら「たるさんとこへ行ってきィ」と声かけて。
エストレラ津田サッカ-クラブ 令和2年4月春号
「子育てママ塾」
エストレラ津田の総会が延期になりお母さんたちと会える機会も延びました。
「子育てママ塾」として伝えたかったことをまとめてみました。
新コロナ感染症には勝つには「我慢」と人に対する「優しさ」が不可欠です。
しかし子どもも外にも出れずストレスを抱えて、親の言うことを聞かなくなり
兄弟ゲンカ等が始まると「わかってはいるが、、、」いらだちが積もりに積もり
否定的な言ってはいけない言葉まで出てしまうものです。
私は子どもたちに46年間伝え続けていることは「人のために」です。
子どもたちが「僕はこんなことをして〔ありがとう〕と言ってもらえたよ」と
友だちや家族、世の中に貢献していると実感できる子どもに育つてほしい。
それには子ども自身が自分のことを認め自分を好きになる「自己肯定感」が
必要で「僕は親(母親)に愛されているなぁ~」という安心付きの実感(保証)
がないと「自己肯定感」は生まれません。
神様は一生のうちであるかないかの緊急事態の中で「子どもや家族と向き合う機会」
を与えてくれてると思うんですが、、、、
*人間誰しも泣きたくなる程の困難や苦しさにぶつかった時、先にある「希望」が
あるから乗り越えられる。こんな時だからこそ「明るさ」と「希望」がわく
「ネガティブ言葉、おかげ言葉」で過ごしましょう!!
今日から嫌なことばを一切使わないと約束(出来なければ罰でも設けて)して
お母さんがイライラし言ってしまいそうになると呼吸法や顔を洗うなどして
以下はお母さんから子どもへの褒め言葉例です。子どもに負けないで下さい。
「ありがとう」「やったね」「さすが」「できたね」「よくがまんしたね」
「うれしい-っ」「サンキュ」「ラッキィ-」「なるほど」 「へぇ-」
「あんたのここが好きやわ」「それ、いいなぁ~」
「(部屋)がきれいになったね」「(玄関の靴)並べてくれてありがとう」
「今日はいつもと違うね」「そこがいいとこやで」「あんたのおかげや」
*できなくても
「きっとできる」「だいじょうぶ」「残念、でもやってみることが大事なんや」
*どうにもできない時
「なんとかなるよ」「おかあさんもそんな時あったわ」「いい経験になったね」
※〔親と子ども一緒に〕過ごし方(提案)※
〔1〕毎日やること(1)読書(2)日記(20分間)*続けて下さい。
〔2〕その日にやること
(1)アルバム整理(ベスト3選) (2)料理(メニュ-選びから片づけまで)
(3)屋内外一斉掃除 (4)親子ゲ-ム大会(子どもに負けない)
(5)家族の(長所)発表会 (6)今までの「思い出ベスト10」発表
◆お願い◆
*5、6年生対象に毎年「こころ塾」を実施していますが、しばらくは保護者に
ラインにてテ-マを告知しますので子どもたちに伝えて下さい。
○令和元年「子育てママ塾」まとめ
(1)胎児期・・・望まれて産まれたか?
体を通して自分は歓迎されてないと世の無情を感じながら産まれてくると
成長するに従い問題行動を起こす。
その子の「人間回復」はその後出会った人の「愛情」で変えれる。
(2)乳児期・・・親から愛情持ってお腹いっぱい「お乳」を飲ませもらったか、、、
人生最初の贈り物である食べ物の恨みは恐ろしく一生続く。
〔母乳、哺乳瓶でも〕口からの愛、抱っこ、触れて、あたたかく、ゆったりと。
〔不足なら〕指しやぶり、髪いじり、チック(大人になると)飲酒、喫煙、薬物
(3)乳幼児期・・三つ子の魂百まで=3才までに受けた愛情を一生持ちつづける。
〔スキンシップ〕*おんぶ、だっこ、手をつなぐ、触れる、寄り添う
〔居心地(情緒安定)〕*散歩、夕陽、星、雨、草花(自然の中で)童謡、絵本
(4)幼児期・・・5才までに神経系が80%育つことから「遊び」が大事
〔神経系=感覚系〕リズム、バランス、タイミング、センス、敏捷性を養う
(5)幼児期までに「愛情不足」のままの育った子どもが取る行動は
*手がかかる、静かにできない(しゃべる)立ち歩く、集中力がない、
こだわり、孤独、我慢ができない、集団に合わせられない、反抗、奇声など
◆幼児期に「愛情不足」と感じた親の役目は◆
〔結論〕優しく、見つめる、微笑む、話しかける、ほめる、触る、甘えさせる。
※子どもの行動には意味があり、意味のない行動は取らない※
*子どもは「脳や心」を快適に安定させるために行動を取る。
親、教師、大人は
ア:子どもにしてほしくない行動を取れば ・・・「やめなさい」と注意し怒り
イ:子どもがやってほしいことをしなかったら・・「~~しなさい」と指示し叱る。
「脳や心」を快適に安定したい子どもに〔注意、指示、叱責〕で行動を止めれない。
「怒る、体罰」などで強制的に子どもの行動を止めれば「脳や心」が迷走して
不適応を起こし身体症状に出たり、パニックや問題行動を起こす。
◆子どもが「愛情不足」のまま我慢し抑圧し続けて第2反抗期(思春期)へ◆
(1)反社会的行動(問題行動、非行、ワル)に出る。
ア:問題行動を起こす子どもには校則通りの謹慎、反省文、説諭では解決しない。
イ:解決するのは原因を探ること。それには子どもの幼少期を知ることから始める。
ウ:子どもの「心の奥」に潜む問題(心の病)に気づき感じることを怠らない。
(2)非社会的行動(登校拒否、不登校、自殺)に出る。
ア:心と体が分離できない思春期に中1~中2に起きやすい。
イ:指導しよう、治そうとか、学校へ戻そうと考えず〔思い〕を聞き続ける。
その時「なぜ?」とは聞かない。逃げ出していい無理をしなくていい、、、と。
ウ:非社会的行動を取る子どもは
※感受性の強さと気づきと優しさの犠牲者※
誰だって楽しく学校に行きたい。みんなとすごして適当にごまかして生きれば
いいのにそれができず「気がつき(繊細)すぎて」苦しんでる。
エ:たった一人で(自分探しの旅に)大人でもできない自分自身と向き合ってる。
長期に、何年も、時には死を考えるまでも。だからえらいしすごい。
〔結論〕親、教師、大人の役目は「見つめる、微笑む、ほめる」に尽きる
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
*エストレラ津田及びエストレラ姫路保護者対象「子育てママ塾」並びに
市川町主催人権教育講演会「子どもの人権」より抜粋。