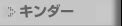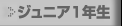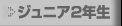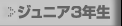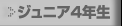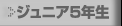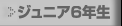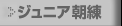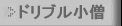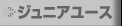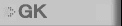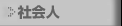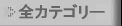2025 年 04 月 15 日 更新
令和7年度 育成会総会について
下記の案内を確認していただき、合わせてホームページ内にあります津田サッカークラブ概要【理念・方針・育成会会則・朝練習・年間行事について】事前に熟読していただきますようお願いいたします

2025 年 04 月 13 日 更新
緊急連絡 キンダー新1年生体験案内-訂正版-
2025 年 04 月 05 日 更新
令和7年度 新規入団要項・申込書(キンダー・新1〜6年生)
1番下よりダウンロードできますのでプリントアウトしてご覧ください
2025 年 04 月 05 日 更新
令和7年度 津田SC 概要
2025 年 04 月 03 日 更新
キンダー・新1年生 体験ご案内
2025 年 02 月 06 日 更新
新3年生 サッカー用具注文書
新3年生(現2年生団員へ)
申し込み期限は、2月末日。ダウンロード、プリントアウトし必要事項記入の上、上部を切り取り、学年連絡委員へ提出してください。(団へは3月2日期限)

2025 年 02 月 01 日 更新
令和7年度 登録継続希望者へ
令和7年度 登録継続用紙
来年度も継続希望の方は、用紙をプリントアウトし、各項目をご確認の上、必要事項を記入し停止をお願いいたします。
登録継続用紙と費用を添えて、各学年の連絡委員へ 2月16日(日)までにご提出ください。

2024 年 04 月 29 日 更新
令和6年度 ジュニア途中入団 要項・申込書
2024 年 03 月 29 日 更新
ジュニアユース(中学生)体験練習案内
体験練習会を実施しています。
日時・会場については活動予定表→ジュニアユースを参照ください。
希望者は事前連絡が必要ですので西澤(09034879366)までお願いします。
2024 年 03 月 28 日 更新
令和6年度 キンダー入団要項・申込書